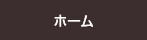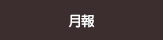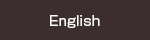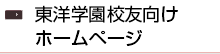2012年度4月 月報
2012年4月25日
往訪:旧制東洋高等学校ドイツ語教授、故奥住綱男先生(1923~2000)ご遺族(つくば市:奥住園先生、有田里加先生)。
東洋女子歯科医学専門学校23回生石川総子先生のご紹介で、故奥住綱男教授夫人の奥住園先生(東洋女子歯科医専23回生、歯科医)とご長女の有田里加先生(皮膚科医、ご夫君は東邦大学医学部教授)のお宅を訪問しました。
奥住綱男先生は学徒出陣(14期海軍飛行科専修予備学生)を挟み1947年に東京帝国大学文学部ドイツ文学科を卒業。川端康成らが主催した鎌倉文庫に編集者として勤め、1948~1950年に旧制東洋高等学校ドイツ語教授。学生寮「茜寮」の寮監として津田沼校舎に住み込みました。その後は宇都宮大学、千葉商科大学で教鞭をとり、千葉商科大学を設置する学校法人千葉学園の理事・評議員を3期12年務めています。また、同人誌に小説を発表して『川風』は1956年度の直木賞候補に挙げらました。
旧制高等教育機関の師弟関係は濃密です。旧制高校理科乙類(医学部進学課程)の第一外国語はドイツ語、寮監として24時間学生と接していたこともあり、終生旧制東洋高校卒業生との縁を持ち続けました。同校同窓会ならしの会記念誌『ならしの』(1994年)に、奥住先生が「『ならしの抄』のこと」という随想を寄稿されており、これをもとにお話を伺いました。
教員の立場によるご証言、資料、写真などを(夫人の場合は学生としての立場からも)数多くご提供いただきました。茜寮に鎌倉文庫の同僚だった遠藤周作がしばしば出入りしていたことなど、興味深いエピソードが数多くあります。
専門教育のみに任じていた旧制医専・歯科医専が大学となるために必須のもの、それが教養教育でした。教養教育は教養課程、予備教育、進学課程など呼称はさまざまながら、旧学制では専門課程の大学に進学する上で高等学校か大学予科で教養教育を受けることを必須とされ、それが新学制では大学の中に包摂されて教養部、一般教育科目になりました。
広範な教養に加え、日本の場合は欧米先進国の知識、技術を修得するため外国語の学習が重視されました。今日は教養、教養教育の定義すら曖昧になりましたが、当時の教育現場の実相を掘り起こすと、旧制高校(予科)の教養教育が人格形成に大きな役割を果たしていたことが理解できます。本学(東洋女子歯科医専)が大学昇格不可となって旧制高校を設けた頃、昇格した歯科医専は大学予科を設けましたが、東京歯科大学は「ここ(註:大学予科)で学んだ人たちの人生における不滅の一章となっている」(創立120周年記念誌,2011年)と総括しています。
大学史には直接関係ありませんが、卒業生、教員ご遺族の調査では関連して家の歴史も伺うことが多く、今回も奥住園先生のご実家の、医家としての歴史は興味深いものでした。
2012年度ミニ企画展(特集)「最後の旧制高校、東洋高等学校」